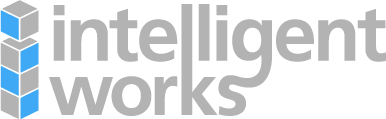◆ はじめに:「APIって何?」からはじめよう(会計ソフトAPI)
DXや業務効率化といった言葉とともに、「API連携」「会計ソフトAPI」という言葉を耳にすることが増えてきました。
でも、「そもそもAPIって何?」「本当に必要なの?」と疑問に思っている方も多いはず。
本記事では、**「APIってなに?」から始めて、会計ソフトと連携することで何ができるのか、導入のメリットは何なのか」**を、実例を交えてわかりやすく解説します。
◆ 会計ソフトAPIとは?
API(Application Programming Interface)とは、**アプリやシステム同士をつなぐ“データの橋渡し役”**です。
会計ソフトAPIとは、次のような仕組みです:
「他のシステムから会計ソフトに直接データを送ったり、受け取ったりできるようにする機能」
例えば、請求書発行システムから売上データをAPI経由で自動連携すれば、手入力をせずに会計ソフトにデータが入るようになります。
◆ 何ができる?APIで実現できる主な機能(会計ソフトAPI)
会計ソフトのAPIを使えば、次のようなことが可能です:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求書データの登録 | 外部システムから発行した請求書を会計ソフトに自動で登録 |
| 仕訳の自動作成 | 経費精算や売上情報から仕訳データをAPI経由で生成 |
| 入出金データの取得 | 銀行APIや決済サービスと連携して入出金を取り込み・照合 |
| マスタ情報の取得/更新 | 取引先や勘定科目などのデータを同期・管理 |
| 会計データの出力 | 月次レポートやBIツールへの連携用データを自動抽出 |
◆ 導入・開発の5つのメリット
✅ 1. 入力作業の削減とミスの防止
手入力やCSVインポートの手間が減り、人的ミスも激減。
経理担当者の負担が大きく軽減されます。
✅ 2. 業務スピードの大幅向上
データ登録・処理・集計までがリアルタイムで行われるため、月末の締め作業も短縮されます。
✅ 3. 他システムとの連携で“つながる業務”に
販売管理、勤怠、経費精算などとスムーズにつながることで、全社の業務が効率化されます。
✅ 4. 法令対応の自動化がしやすい
電子帳簿保存法やインボイス制度などにも、API連携によるデータ保存や処理でスムーズに対応可能。
✅ 5. 属人化の解消と標準化
人に依存しがちな手作業から脱却し、“仕組み”として動く経理体制を構築できます。
◆ よくある導入シーン・実例(会計ソフトAPI)
📌 ケース①:請求書システムとの連携
- 販売管理システム → 請求書発行 → 会計ソフトへ自動仕訳
- 月に数百件ある取引データを自動で反映、確認のみで済む
📌 ケース②:クラウド勤怠・経費サービスと連携
- 従業員が入力した経費情報から、自動で会計処理へ反映
- 申請・承認・仕訳まで全体が一気通貫に
📌 ケース③:銀行APIとの連携
- 銀行の入出金をリアルタイムで取得 → 自動で仕訳に変換
- 毎月の“通帳突合”作業がほぼゼロに
◆ 対応している主な会計ソフト
近年、多くのクラウド会計ソフトがAPIを公開しています:
- freee 会計:APIの範囲が広く、豊富な外部連携実績あり
- マネーフォワード クラウド会計:経費・請求・勤怠などグループ製品とのAPI連携に強み
- 弥生シリーズ(API対応版):外部開発者向けの開発環境あり
導入時は「APIドキュメントが公開されているか」「テスト環境があるか」などもチェックしましょう。
◆ 導入の進め方:かんたん3ステップ
- 自社の業務フローを可視化
→ どこが手作業で、どこを自動化できそうかを洗い出す - 使用中の会計ソフトのAPI対応状況を確認
→ 利用中のツールとの相性をチェック - IT部門または開発パートナーと連携開発をスタート
→ 社内外の技術リソースを活用し、安全に構築
◆ まとめ:API連携で「経理の働き方」が変わる
会計ソフトAPIを使えば、ただの便利機能を超えて、
- 作業時間を削減
- 人的ミスを防止
- 組織全体の業務スピードがアップ
- 経理の役割が“確認と戦略”に進化
といった大きな変化をもたらします。
デジタル化は“道具”を入れるだけでは進みません。
道具同士がつながって、はじめて「業務が変わる」=DXの第一歩になります。
(参考:弊社の開発・サービスについて)